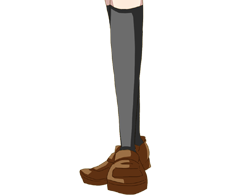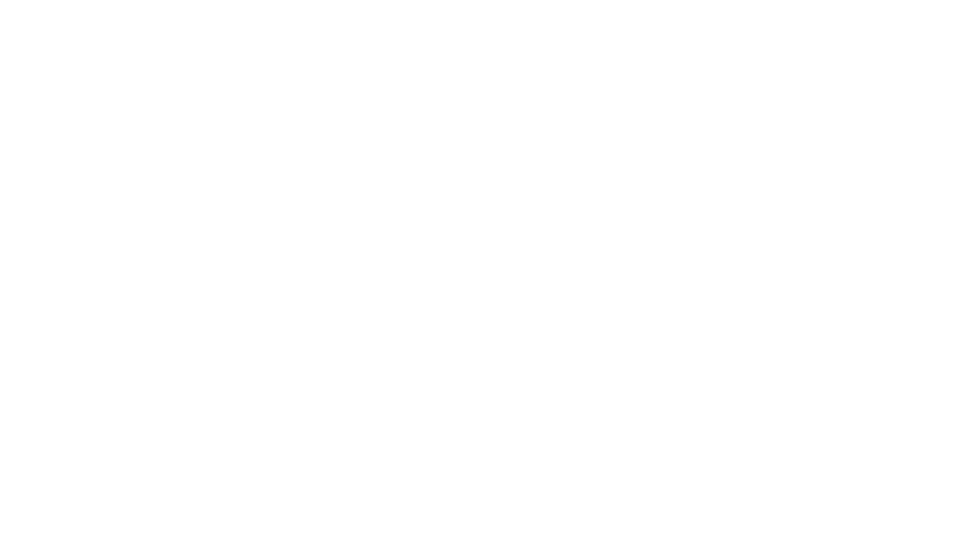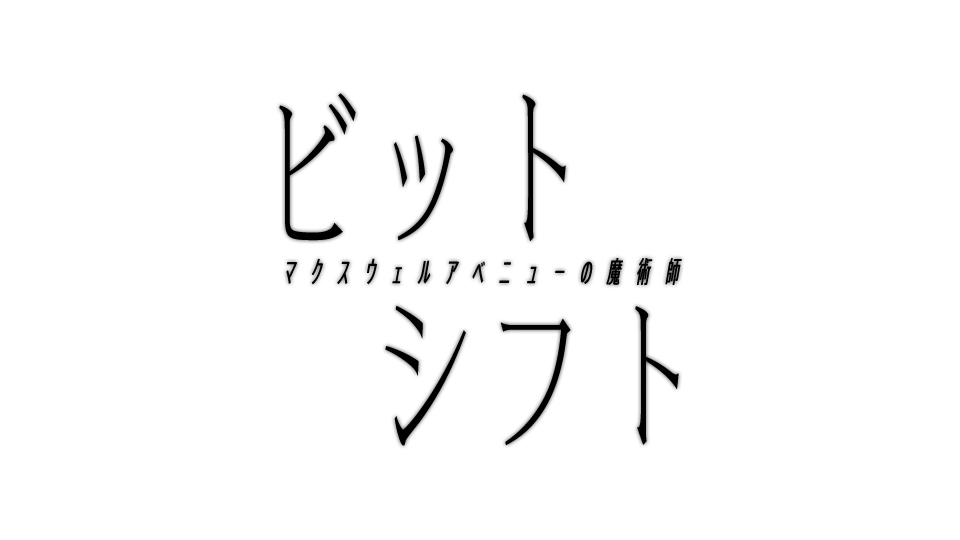
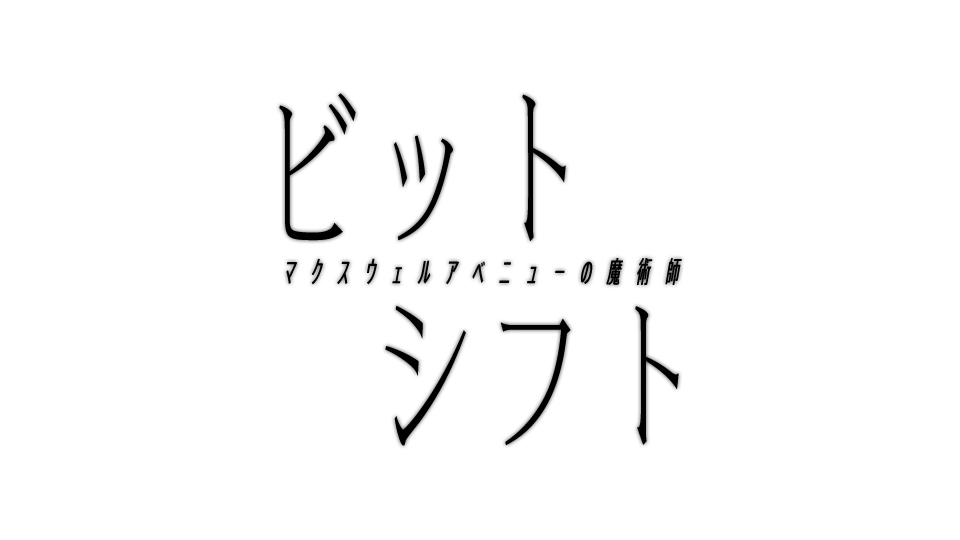

act5-B

サーチの正体


翌日、昼休み。

ウィリアムが生徒会室に足を運ぶと、サナエの姿が無かった。

エリカもまだ来ていないようだ。代わりに、机の上にはメモと、弁当らしき包みがひとつ。

『クラスの用事ができたので、ちょっと遅くなりそう』

『あと、これはエリカと一緒に作ったランチです。待たなくていいから、先に開けて食べててね。 サナエ』

「あ……」

丁寧に包まれたランチボックスを見て、昨日のことを思い出した。

全く、昨日は一日で三日分くらいの事件があったから、エリカのケーキ作りを手伝わされたのがまだ昨日のことだなんて、不思議に思える。

このメッセージを見る限りでは、ケーキは無事渡せたみたいだ。

一緒に弁当作りができたということは、きっとエリカは喜んでいるだろう。

心なしかホっとしながら、ウィリアムは机にドンと持ち込んだ荷物を置いた。昨日の紙袋だ。

「……ランチは先輩が来てからでいいか」

ごそごそとゴーグルを取り出す。実は、昨夜のうちに既にソフトの入れ替えは済ませてあった。

帰宅してすぐに寝てしまうつもりが、怒りが収まらなくて仕方なく延々とセットアップをしていたのだ。

慣れないシステムでまたもや朝方までかかってしまったので、まだ動作は確認していない。

本当は、最初に使う時はSiNEルームでサーチに確認しながらにするつもりだったのだが、今日は彼女を呼び出すことが出来るかどうかすら怪しいし、昨日の今日ではとてもそんな気にもなれない。

ここから先は一人でやってやると、ちょっと意地になっている部分もある。

「よし……」

昨夜、別れ際に男が「ゴーグルを使うな」と叫んでいたので、余計にやる気になっていた。あんな嫌な奴の思う通りになってやるものか。

眼鏡を外して、ゴーグルを付ける。サングラスのように色のついたグラス越しに、生徒会室の風景が見えた。

電源を入れるとそれに被さるように起動メッセージが表示され、同時にフッと明かりが堕ちるように外の風景が見えなくなった。

この機械はもともとネットワーク端末なので、起動すると自動的にΩ‐NETに接続するようになっている。

形態こそ違えど、基本的にその辺りは家で使っているテーブルトップとさほど変わらない。

(えと……ネットに接続したら、ここで……確か、選ぶ……)

搭載されているOSは、サーチに資料を出してもらった時に一緒にダウンロードしておいた改造版だ。

ユーザー認証の途中で、接続モードを尋ねるダイアログが出てくるので、そこで1ビットモードを選ぶ。

──認証成功。ゲートウェイからウエルカムのメッセージが流れるのを見て、期待に胸が高鳴った。

「よし……あ……うわっ!?」

成功したと思った瞬間のことだった。

まず、耳が聞こえなくなった。

昼休みの騒がしい廊下の喧騒が、ぐっとボリュームを絞ったようになって、プツリと途絶える。

聞こえない、と、思った瞬間手足の感覚が消える。

今の今まで椅子に座っていたはずなのに、立っているのか座っているのかも判別できない。

まるで自分の身体が無くなったみたいだった。

(な……何……これは……)

声も出なかった。

見開いた目の前には、夜空のような果ての無い空間。上を見ても、下を見ても終わりが無い。

いや、自分が見ているのが上なのか下なのかも分からない。


もがこうとしても手が思うように動かなくて、そのくせ目を動かす度にぐるんぐるんと視界が回転する。あっという間に気分が悪くなってきた。

《ホストを移動します》

唐突にアナウンスが聞こえたと思うと、その場に浮いた感覚のあった身体が、急に落下しはじめる。

(え……ちょ……っと、待ってって!)

二秒、三秒、四秒、五秒……落ちる感覚が終わらない。

何だ、これは。

自分は今生徒会室の長机に座っているはずなのに、どうして全部の感覚が別のことを感じているんだろう。

落ちる。落ちる。

だんだん目の焦点が合わなくなって、頭がガンガン痛んでくる。

これは、一体、どうすればいいんだ。

本体の電源を切れば接続は強制終了するはずだけど、そもそも今の自分の感覚では、頭にゴーグルなんて付いていない。

死に手を動かして頭のあたりを探ってみても、やはり、電源なんてどこにもありはしなかった。

《ホストを移動します》

再び、同じアナウンス。

(何、また……!?)

刹那、ピタリと落下が終わる。

今度は身体がフワッと浮き上がり、そのまま落ち葉のようにクルクル周りながらどこかへ持っていかれる。

(────!!!)

身体が回転しすぎて、もはやどちらが上だか下だか分からない。

大きな波か、荒れ狂う濁流にでも呑み込まれたら、こんな感じがするのかもしれない。

もしかしたらこれは、何か重大なことを間違っているのではないか。

昨夜あの男の話を最後まで聞いておくべきだったのだろうかと、後悔の念が途切れ途切れに思考に混ざる。

(────…………)

しかし、まもなくその思考も保てなくなり、少年は意識を手放していった。


「──はぁ、こりゃ、本格的にやばいな」

薄暗い部屋、ホログラフィウインドウの青白い光を睨んで、男はポツリと呟いた。

「どうした、ハロルドよ」

隣の部屋からしわがれた声が男の名を呼ぶ。

ベランダの傍の、いつもの定位置に陣取ったジョージは、熱心に何かの機械を組み立てているようだ。

「いやな、昨日話したあの坊主、もうゴーグルを組んじまったらしい。今さっき、あいつらしい異常終了のログが……」

ウインドウから目を放さず、ハロルドは言った。

「だぁから、儂が言ったじゃろう。お前さんが忠告を聞かないからじゃ」

ジョージに睨まれて、ハロルドは少し困ったように目を泳がせた。

「それについては甘かったと思ってるよ。勘弁してくれ」

「ほほぉ、珍しく殊勝じゃのぉ。しかしまあ、なかなか見どころのある少年じゃないか」

ジョージはあっけらかんと言う。

「しかしなあ、あんなもんそのまま使って、下手すると死ぬぞ?」

「お前さんが他人の心配たぁ、珍しいな」

拡大鏡を覗き込んだまま、ジョージの枯れ木のような手は恐ろしく細かい作業を続けている。手を入れているのはハロルドのゴーグルのようだった。

「ジョージ、人のことを冷血人間のように言わないでくれよ。俺だって十六の子供を死なせるのは気が引ける」

深くため息をついてハロルドは言った。

「お前さんのせいじゃないだろう」

「なんだよ、今さっきは俺のせいだって言ったくせに」

「別に、そういうつもりでは言っとらんよ、ちょっとばかり、迂闊だったと言っとるだけじゃ」

「なんだそれ」

「技術はいつだって公平なんじゃよ。子供だとか、大人だとかは関係ない。そりゃ、場合によっては命がかかることだってあるさな」

好々爺的優しげな風貌とは少し乖離した、技術者らしい突き放した冷静さで、ジョージは言った。

「そりゃそうだが……」

ハロルドは画面に目を戻し、複雑そうに目を細める。

「やっぱり、昨日ちょっとからかい過ぎたからな。俺も、まぁ、大人げなかったかなーと……」

リビングの真ん中にドンと置かれた、古い革のソファに沈み込んだ体勢で、長い足を組んだハロルドは落ち着かない。

「お前さんはいつだって大人げないじゃろうが」

「……うるさいな」

子供じみた表情で文句を言うハロルドを横目に、ジョージは何食わぬ顔で作業を続けながら言った。

「なぁに、運が良ければ死なないし、死にかけたくらいで諦めるようじゃ、1ビットダイビングには向かんよ」

呵呵と笑って、ジョージは仕上がったらしいゴーグルをハロルドに投げて寄越す。

「ま、それでもちょっと気の毒だがな。何しろ、いきなりお前さん用のチューニングでダイブしちまったんじゃろ?」

投げられたそれを片手でパシリと受け取って、ハロルドはちょっと眺めてからおもむろに電源をいれた。

「全く、ガキってのは短気で嫌になる……ああ、これならいけそうだ。悪いな、いつも」

「構わんよ、お前さんの注文はいつも面白いからな。エンジニア魂が疼くよ」

「じゃあ、ま、ちょっとサルベージしてくる」

「あいよ」

ハロルドがΩ‐NETに意識を沈めていくのを確認し、一仕事終えたジョージはそう言いながら手元のプレイヤーのスイッチを入れる。

まもなく、お気に入りらしいテクノ・ミュージックが流れだすと、上機嫌で次の作業に取り掛かった。


《脳波異常により強制終了しました。電源を切って処置してください》

《脳波異常により強制終了しました。電源を切って処置してください》

《脳波異常により強制終了しました。電源を切って処置してください》

ゴーグルに付いた小さなスピーカーから、しつこく繰り返されるアラートをサナエが聞いたのは、昼休みも後半に差し掛かり、用事を終えた彼女が生徒会室にやってきた時のことだった。

はじめ、ドアを開けて部屋に入った時、誰も居ないように見えたので、少女は微かに落胆した。

しかし、

「ウィル!?」

アラート音がする方を見ると、ゴーグルをかけたままの少年が床に倒れていたのだ。

椅子から落ちたのか、彼の傍には座っていたらしいパイプ椅子が転がっており、倒れたウィリアムはピクリとも動かない。

「ちょ……何、ウィル? どうしたの!? ウィル! ウィル!!」

サナエは取り乱して少年を抱き起こすと、必死に呼びかけた。

しかし、返事は無い。彼の身に何が起こったのか、全く予想すらつかないまま、少女は青ざめた顔で電源を切るようにとアラートの鳴り続けるゴーグルの電源ボタンを必死に探す。

机の上には、サナエとエリカが作ったランチが、手を付けられることの無いまま残されていた。


1ビットモードで見るΩ‐NETは、宇宙に近い、と、ハロルドは思っている。

限りなく無限に近い空間に、飛び交う光子の群れが描く光の軌跡。

正式稼動がはじまって既に数百年、一瞬も止まることなく動き続ける、世界を満たす情報の集合体。

小さなひとつひとつが全て意味を持って流れてゆく様は美しく、視覚情報に変換されて眼前に広がる風景は、荘厳とすら思える。

今はまだ、彼にしか見ることが許されていない世界だった。

「えー……っと、どこだ……?」

少年の反応が途絶えたポイントを探しながら降りてゆく。

視覚化されたデータサーバの中を探る作業は、ダイビングという名にふさわしく、まさに深海に潜るようなものだ。


「居た……」

少年の姿をしたそれは、1ビットモードによって体から切り離された、彼の意識である。

「あーあ、伸びてやがる」

ぐったりと力の抜けた身体を無造作に抱え上げる。勿論、その体に重さはない。

何かのコマンドを手早く入力し、実行すると、次の瞬間には少年の身体はぼうっと光り──次の瞬間には無数の光子に分解され掻き消えていった。

「はぁ……」

ハロルドはホッとしたように息をつく。

《サルベージ、成功したか?》

音声に合わせて、周囲の光子がざわめいた。ジョージからの通信のようだ。

「ああ。まぁ、大丈夫だろ」

《良かったなぁ、ハロルド》

「……なんだよそれは」

からかうようなジョージの言葉に、ハロルドは憮然として目を細めた。


──遠く、チャイムの音を聞いた気がした。

一体いつごろから自分はこうしているのだろう。

気が付くと、真っ白な世界を一人で漂っている。

体が羽根のように軽い。

死んで魂だけになったらこんな感じなのかもと、ぼんやり物騒なことを考える。

このあやふやな世界がどこなのか、どうしてこんな所に自分が居るのか、はっきりと思い出すことができない。

自分は元々ここに居たような気もするし、そうでなかった気もする。何もかもがいい加減で曖昧だった。

(……気持ち良いな)

──考えなければならないことがあったような。

(そういえば……ランチ、食べないと)

──そんなことだっただろうか?

(褒めないと、エリカとサナエ先輩、絶対、怒るし……)

思い出す。可愛らしい模様の入った布できちんと包まれた、二人分のランチボックスだ。

あれを食べようと思っていたんだ。先輩たち、最近料理にでも凝ってるんだろうか。

(ああ……そうだ……)

そこまで考えてやっと繋がる。

生徒会室でゴーグルを使って──そして、失敗したんだ。

1ビット・ダイビングが危険だなんて思ってもみなかったことだけど、実際やってみて理解した。

意識と感覚を直接Ω‐NETに接続するというのがどういうことなのか。あの男がやめろと言っていた意味も、今ならよく分かる。

(ああ、もしかして、じゃあ……死んだ?)

痛みも苦しみも無いので、自然とそんなことが思い浮かんだ。

死んだとしたら困ったなあ、と、少年は思った。

何より、両親が悲しむ。母さんなんか、僕が死んだりしたらどうなってしまうんだろう。

それに、せっかく用意してくれたランチを食べずに死んだりしたら、二人は怒るに違いない。困ったなあ。

あと、できれば、もう一度サーチに会いたかった。

何だか不本意な感じで途切れてしまって……別に彼女に対して怒ったりしてないから、それを伝えておきたかったな。

暢気に自らの死について考えを巡らせているうちに、不意に、白が途切れた。

「…………?」

目が開いていた。天井が見える。そして、体があった。

ベッドに横たえられているようで……かけられた布団が暖かくて少し重い。

「あ……」

かすれた声。自分の声だ。

「……ウィル?」

すぐ近くで、女の子の声がした。

そっと視線を移すと、自分を覗き込んでいる、サナエの顔があった。

「先輩……」

身を起こすと、ベッドの脇に座っていたサナエがカタンと立ち上がる。

「あ……」

艶やかな黒髪が頬にかかる。ずっと窓際に座っていたのだろうか、差し込む太陽に暖められた、甘い日なたのにおいがした。

「馬鹿! もう、冗談じゃないわよ! もし起きなかったら……どうしようかと……!」

癇癪を起こしたような言葉と反対の行動。少年の体を抱きしめて、それきり黙り込んでしまう。サナエの肩は震えているようだった。

「……すみません」

ちょっと息苦しいけれど、文句は言わずに素直に謝る。それから、先程夢の中で考えていたことを思い出して、

「……ランチ、食べちゃいました?」

冗談っぽく尋ねてみた。

「え?」

サナエは拍子抜けしたように力を緩めて、ウィリアムを覗き込んだ。案の定泣いていたらしい、兎のような赤い目を見つめて続ける。

「先輩が来てから頂こうと思ってて……」

泣き顔のサナエは呆気にとられたようだったが、すぐに

「ば……馬鹿なこと言って……こんな時に、何言ってるの!」

今度は本当に怒られた。

ふと時計を見上げる。十七時。もう今日の授業は終わってしまったらしい。思ったよりずっと長い時間が経っていることに、ウィリアムは改めて驚いた。

「……ウィル?」

壁の方を見て固まっているウィリアムに、サナエが気付いて声をかける。

「もう……夕方だったんですね」

「……そうよ」

少女は苦笑して言った。

「僕……どうなってたんですか?」

ウィリアムは恐る恐る尋ねた。1ビットダイビングをしていた途中から、記憶がぷっつり途切れていたのだ。

「……私が見つけた時にはもう倒れてて、お医者様を呼んで診てもらったんだけど、意識が無い以外は正常だって言われたのよ」

「深く眠っているようなものだから、様子をみてくださいって話で、様子が変わったらすぐ病院に連れていくことになって……」

それで、ついていてくれたわけだ。サナエに午後の授業を休ませてしまったとしたら申し訳のないことだ。

けれど、彼女はそんなことは少しも気にしていない風で、目が覚めて良かったと微笑んだ。

「それにしても」

安堵の表情で、サナエが呟く。

「二度目ね」

しみじみと言ったその言葉に、ウィリアムは不思議そうに首をかしげた。

「……何がですか?」

「あら、やっぱり憶えてないんだ」

サナエはあっさりそう言って苦笑する。

「まぁ、無理も無いか」

「だから……」

「入学試験の日よ」

「え?」

「あなたが今日みたいに倒れて、保健室に運ばれて、私がこうして付き添いをして……みたいなこと」

「あ……」

言われて思い出した。入試の日、確かすごく体調が悪くて、数学か何かの試験が、半分しか受けられなかったのだ。

ちょうど1年くらい前の話で、気分が悪くて──覚えているのは保健室のベッドの、乾いたシーツの感触が心地よかったことくらいだ。

けれど、思い出してみると、確かに誰か、在校生に付き添ってもらったような記憶がある。

「あの時の……先輩だったんですか」

「そうよ」

考えてみれば、入学試験中の雑用は生徒会の仕事だから、サナエが居たというのも、納得できる。

「そんなこと、よく憶えてますね」

「だって、ちょっと衝撃的な病人だったもの」

言って、サナエはクスクスと笑う。

「だって君、再試験の手続きしておこうかって聞いたら、いらないって言ったのよ。まだ試験時間半分も残ってたのに」

「あー……そうでしたっけ。そうだったかも」

ここは、ネオポリスでは屈指のエリート校である。親も子供も必死になって入学試験を受けるのが当たり前なのだ。

「その時は、何て余裕かましてる子なのかしらって呆れたんだけど、そのあと入学式で、君が新入生代表の挨拶したじゃない? よっぽど頭のいい子なのねって、2回驚いちゃったわ」

サナエの言葉に、少年は困ったように笑いながら、ゆっくりと身を起こした。

「たまたまですよ。数学は得意だったから」

言いながら、跳ねた髪を気にするように頭に手をやる。その仕草に、サナエは少しだけ不安そうな色を見せた。

「痛いとことかない? もう少し寝てれば良いわよ」

「大丈夫ですよ、どこも平気です。それより先輩、ランチにしましょう」

「は?」

間抜けな声をあげてから、一瞬遅れてウィリアムの言葉の意味を理解したらしい。サナエは赤くなって、それから必死に首を振る。

「も、もう夕方だから! だめだめ!」

「ええ……もったないですよ」

「だめだめ、これ以上何かあったら嫌だわ、ま……また明日、作ってくるから!」

サナエは大げさに拒否したが、ウィリアムは引き下がらなかった。

「もうこんなに涼しいんですし、そんな簡単に悪くなったりしないですって。それに、エリカにも感想伝えないと、明日怒られそうだ」

サナエは何をそんなに気にしているのか、小さくなって俯いてしまう。

「サナエ先輩、お願いします。お腹空いたし、食べたいから」

「あ……」

「手作りなんだし」

困り果てた顔のまま、サナエは目を丸くした。それから、きょろきょろと辺りを見回し、少女には似合わない気弱な顔で、自信なさそうな声で呟く。

「……お腹痛くなっても知らないわよ?」

「はい」

「時間経ってるし、食べてから苦情は受け付けないからね?」

「はいはい」

その様子が本当に彼女らしくなくておかしかったので、ウィリアムは笑いながら頷いた。

中庭に面した明るい保健室に、色づきはじめた夕方の光が深く差し込んでいた。


弁当を取ってくると言ってサナエが部屋を出ていったあと、ふと、枕元に自分のゴーグルが置かれているのに気付いた。

手に取ってみると、何やらランプが点灯している。

「あ……これは……」

チカチカと瞬く、緑色のインジケーター。おそらくメールの着信を伝えるものだろう。メール? 誰だろうか。開いてみようと思った所で手がとまる。

「う……」

昼休みの悪夢が思い出される。あんなのはもう二度とごめんだ。

「……1ビットモードにしなければ、普通に使える……はず……」

おそふおそるゴーグルをかけて、注意深く新着メールを開けてみる。

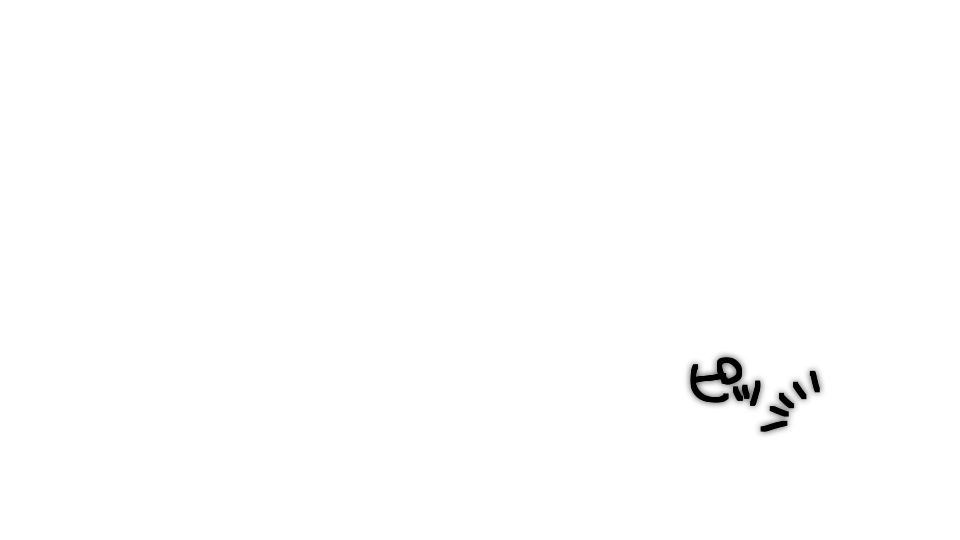

《命拾いしたなら、潜り方を教えてやるから明日うちに来い。
決して勝手にそのゴーグルを使うな。今度は死ぬぞ。
マクスウェルアベニュー七番街二十四 三〇七号室 Harold》
決して勝手にそのゴーグルを使うな。今度は死ぬぞ。
マクスウェルアベニュー七番街二十四 三〇七号室 Harold》

「な……」

内容から考えて、昨夜のあの男からのメールだろう。

偉そうな言葉が思い出されてムッとするが、それよりも、男が少年が1ビットダイビングに失敗したことを知っているような文面に、首をひねる。

どうしてアイツはそんなことを知っているんだ。

「……教えてやる、って……」

本当だろうか?

信用はできない男だと思う。けれど、Ω‐NETについて少年の知らないことを沢山知っている、ということだけは確かのようだ。

「どうしよう……」

マクスウェルアベニュー……といえば、ガイアポリス北側の地区だったはず。うちに来いと言ってきているのだから、この住所が男の自宅なのだろう。

行くとも行かないとも決められないうちに、グラスの向こうでガラリとドアが開いて、かばんを抱えたサナエが入ってくる。ウィリアムは慌てて端末の電源を切って、ゴーグルを外した。

「エリカも探したんだけど、今日はもう、帰っちゃったみたい」

「じゃあ、彼女にはまた、明日お礼を言っておきます」

「あと、一応試食してみた。大丈夫だと……思う」

恥ずかしそうに笑うサナエは、少年がそそくさとゴーグルをベッドに置くのに気付かなかったようだ。

「ふふ、楽しみです」

とりあえず他のことは置いておいて、ありがたく味わうことにしよう。

今度は死ぬ、なんて恐ろしげなことがメールには書いてあったけれど、幸い身体はどこもおかしくはなっていないようで……

サナエと遅いランチを楽しんだあと帰路についた時も、痛みや不自由を感じるような所はなかった。

その答えを知る術は、ひとつしかなかった。

To be continued.