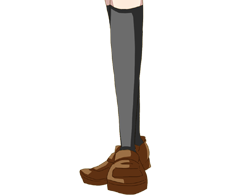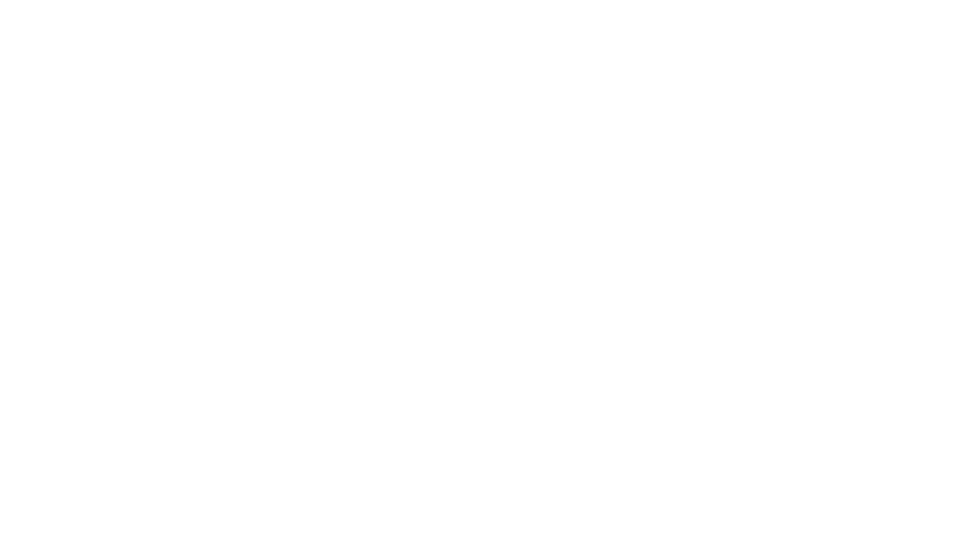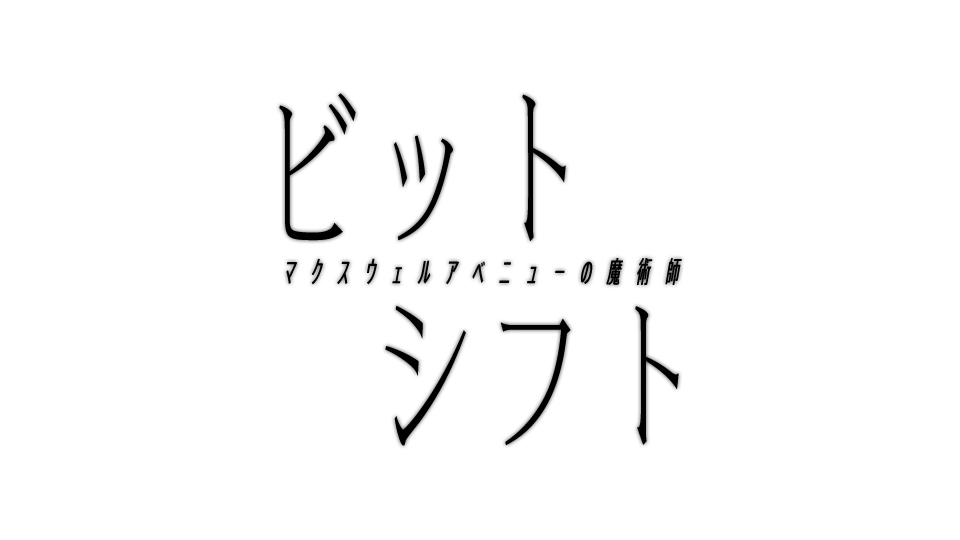
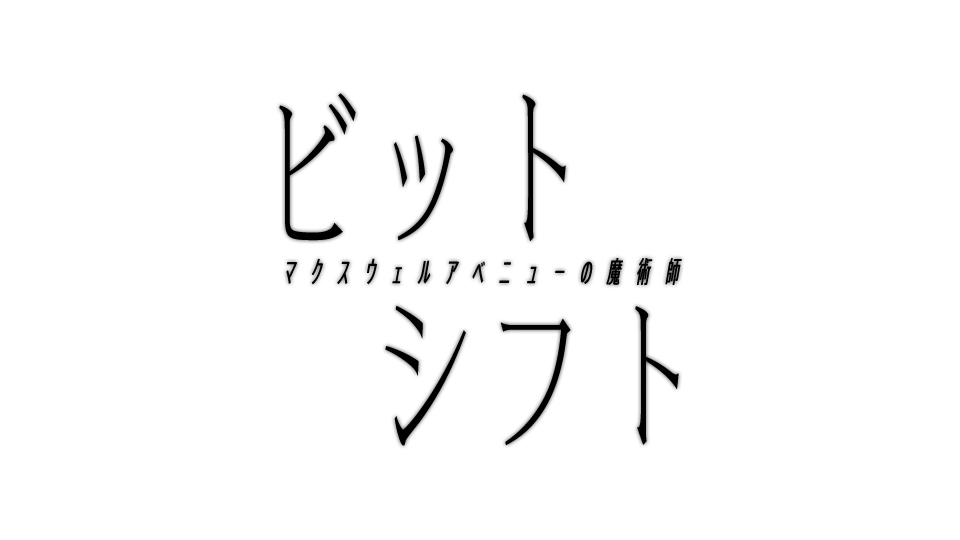

act5-A

サーチの正体


「あ…………」

引き止める間も無かった。

取り残された少年は、唖然としたまましばし少女の消えた光の名残を見つめていたが、やがて、自分の手に何か握られていることに気がついた。

「何……?」

真実は常に、求める者にのみ開かれる。
ハル・サウザンドワード
ハル・サウザンドワード

メモの形状をしていたファイルには、その短い言葉に添えて、住所が記されてあった。

深く考えるまでもなく、そこに来いと言っているように思える。

「オークフィールズ……?」

書かれていたのは、この近くの地域の住所だった。きっちりと細かい番地の指定までしてある。

分かりそうな場所だけれど、あからさまに怪しい。

「………………」

これを寄越した相手は、おそらくサーチライトの《本当の使用者》だろう。

どうしよう。

こんなメモを押し付けて去って、自分が本当に足を運ぶとでも思っていたのだろうか。

「……馬鹿げてる」

サーチライトのマスターであり、もしかすると制作者であり、1ビット・ダイビングの出来る人間。

しかし、連邦総務省にハッキングをかけるような相手である。

どんなにすごい技術者だったとしても、そんなの犯罪者じゃないか。信じると、思っているのだろうか。

「馬鹿だよ。絶対」

少年は力なくこぼした。誰に対しての呟きだったのかは、少年自身にもはっきりとはわからなかった。

「……サーチ」

呼んでみると、今となっては妙に懐かしい通常の検索ウインドウがスッとそっけなく現れる。彼女が居ない証だ。

《何をお探しですか?》

「あ……」

不意に寂しい気持ちが込み上げた。

ウインドウを見つめて、それから手に持っていたメモに目を戻す。

オークフィールズ。ここからは遠くない。

「…………地図を」

このまま何も分からないよりは、行って、確かめたいと思った。


校門を出た所で時計を確認する。

二十時過ぎ。家に帰るのが遅くなってしまうけれど、この際もう仕方がない。

(……母さんには後で謝ろう)

SiNEルームで控えてきた手書きの地図を取り出す。

指定された場所まではここから歩いていけない場所では無かったので、乱雑に書かれてあるメモを頼りに、そのまま速足に歩きはじめる。

(一体、ここが何だっていうんだろう……)

サーチライトとの偶然の出会いから、まだそう長い時間は経っていないはずなのに、感覚的には何ヶ月も経っているような気がする。

理不尽に驚くことばかりだけど、何もかもに興味を引かれる、刺激的な時間だった。

だから、確かめずにはいられない。教えて欲しい、君が本当は何なのか。

自然と足が早くなる。

改造しかけのゴーグルは、結局続きの作業が出来ないままに紙袋の中。

これは、サーチに教えて貰って揃えたもの。少年を惹きつけて止まない、捨てられた情報の海へと至る鍵。彼の世界を、照らしてくれるかも知れない可能性の塊だ。

「サーチ……」

あの不思議な少女に感じていた、淡い想い。

それはおそらく恋では無かっただろう。けれど、限りなくそれに近い何かだったような気もする。だから……

「……信じさせてよ」

祈るように呟いて、少年は夜の道を走りだした。

街灯に照らされた走る自分の影が、歩道や住宅の壁に大きく映し出されて、まるでもう一人別の人間が居るように見える。

自然と気持ちが焦ってしまって、追い立てられるように走り続けた。

オークフィールズは高級住宅地として知られていて、道の脇に経つ家々もいかにも金持ちの住居らしい豪華なものばかりだ。確か、学校の知り合いも何人かこの地区に住んでいる。

けれど、指定されたのはこの邸宅の群れの中ではなく、どうやら地区の中でも外れの方らしい。

(どこだ……?)

慌てず、もっとちゃんと地図を確認してから出てくれば良かったかもしれない。と、ウィリアムは遅い後悔の念に呵まれていた。

距離感が掴めず、道は合っているはずなのに、妙に遠く感じる。

だいたい、住宅地というのは、目印の建物とかそういうのが無いのが困る。

いくつか見過した曲がり角は曲がるべきものではなかったはずだし、今走ってるこの道で、間違いは無いはずだけど……

ああ、やっぱりもっとちゃんと調べて来るべきだった。

とはいえ、今更学校に戻るわけにもいかない。自分の書いた地図を信じてどんどん進むと、やがて、ずっと続いていた住宅地が途切れる。

(この辺り……なのかな……)

行き当たったのは、ちょっとした公園のような場所。昼間なら気持ちの良い場所なのだろうが、夜は暗く、森に迷い込んだような心細い気持ちになってしまう。

(でも……たぶん、住所ではこの奥……)

明るい街灯を探してもう一度メモを確認する。この辺りで間違いないはずだ。意を決して、暗い公園の奥へと進んでいった。


「えええっ……!?」

十分後。ウィリアムは思わず声を上げ、約束の場所の前で立ち尽くしていた。

確かに、彼は『ハル・サウザンドワード』なる人物に会っていた。

ただし────その人の、墓の前で。

「………………」

公園だと彼が思ったのは、実は、霊園だったのだ。

森のように作られた遊歩道を抜けると、一面の芝生と、整然と並ぶ墓標。

てっきり場所を間違えてしまったと思いながらも地図が示すポイントまで進んでみたら、この墓に行き当たったのだ。

こんな時に限って無風で、実に嫌な静寂。

千の言葉《サウザンドワード》という名を持つその人は、墓石の語る所によると、今から百年以上も昔の人物であるらしい。

ハルという名前からは、この人が男だったのか女だったのかは分からない。けれど、立派な墓で、丁寧に手入れされているということは、子孫がこの辺りに暮らしている証拠だろう。

じわり、じわりと、背筋が寒くなる。

もしかして、この話、オカルトの類いか何かだったのか?

「じょ……冗談じゃ……無いよ……」

おそらく、あとひと呼吸分も余分に時間があったら、きっと逃げ出していた。

けれど、ウィリアムが逃亡の体勢に入るよりも僅かに早く、その声は少年の思考に割り込んできたのだ。

「──本当に、ガキだなぁ」

残念そうにそう言ったのは、低い、男の声だった。

「!?」

驚いて声のした方を振り返る。大きな桜の木の幹にもたれ掛かるようにして、背の高い男の影があった。

(人……)

自分がものすごく無計画の上に無防備であることに改めて思い至り、背筋を冷や汗がつうと伝う。

少年は口をつぐんで、じっと男の出方を伺った。

見知らぬ男は、暗闇の中で背を預けていた木から離れ、さく、さく、と夜露に濡れた芝生を踏んでこちらへ近づいてくる。

「……ま、正直ちょっと驚いた。今時の子供にも、お前みたいなのが居るんだな」

からかうような声音。

月明かりの下に出てきたその男は、はっきりと容貌が判別できないとはいえ、ウィリアムより随分年上に見える。大人の男のようだった。

「坊主、名前は?」

横柄な物言い。ウィリアムは反射的にムッとして男を睨む。こういう、初対面で偉そうな大人は大嫌いなのだ。

「……あなたこそ、誰ですか」

質問に答えず、あくまで挑戦的な調子でそう返す。虚勢だったが、意地だ。

月を背負った男は、それを鼻で笑ったようだった。

「人のものを盗んでおいて、図々しいガキだな」

「盗む? 何のことです」

難癖つけられた内容よりも、言い方が癇に障った。子供扱いされるのも気に入らない。

幽霊なら嫌だけど、気に入らない人間の大人相手に、怖がってなどやるものか。

「お前が今持ってるソレだよ。エルズで買ったゴーグルだろう」

生意気な少年を面白がるように、男は長い腕を組んで、

「俺の設計図を盗んだのはお前だ」

やはり偉そうに顎で少年を指して言った。

「え……」

「それから、俺の端末を勝手に使ってたよなぁ」

嫌みっぽく言いながら、ニヤリと笑った気配がした。

「な……」

ウィリアムは聡明な少年だ。だから、非常に混乱してはいたが、男の言葉が意味するところを、すぐに理解していた。そして絶望する。

なんということだ。目の前のこの、性格の悪そうな男の言葉を信じるならば……

「サーチのマスターは、あなただと……?」

恐る恐る口にすると、男はちょっと驚いたように首を傾げた。

「ふん、なんだ。ガキだがバカじゃないのか」


一応褒められたようだったが、言い方が全く気に入らない。ウィリアムは憮然として、改めて男を睨み返す。

何なんだ、この男は。嫌な奴だ。

こんな男がサーチを作ったかもしれないなんて、考えただけで虫酸が走る。

それに……ああ、そうだ。そうだった。

「じゃあ、僕をここに呼んだのもあなたですか?」

「ああ。つか、引っ掛かったのはお前だな」

「……騙したんですね」

「ま、そうなるな」

男は笑った。

「卑怯な。こんな……亡くなった人の名前まで持ち出して!」

少年は不快感を顕に墓石を指した。騙すだけじゃなく、故人の名前を勝手に持ち出すなんてどうかしてる。こんな奴、絶対まともじゃない。

「お前、それが誰か知ってるのか?」

怒る少年をよそに、男は暢気な声で言う。

「知ってるわけないでしょう!!」

馬鹿にしてるのか? 少年はますます頭に血が登り、地団駄を踏んで怒鳴った。

「へぇ。教えてやろうか?」

「要りません!!」

少年が激高すればするほど、男はにやにや笑ってそれを面白がっているようだった。

組んでいた手を上着のポケットに突っ込んで、大股に少年の方へ近づいてくる。

思わずギクリと身体を強ばらせる少年を上から覗いて、男はフフンと笑って言う。

「じゃあ、お前が盗んだ俺の端末(サーチ)のことは?」

「う……」

「知りたいだろ?」

図星をつかれて、ウィリアムは黙り込む。

男は目つきの悪い三白眼に、勝ち誇ったような色を浮かべて言った。

「いい出来だろう、俺が作ったんだから」

男は何を言っても偉そうだった。

「マーキュリー型AIは、あなたが作ったものではないはずだけど」

「ほお? 知ってるのか? AIの制作者」

少年を未熟だと決めつけているような男の表情が、いちいち全く……本当に頭にくる。

「知ってますよ! チェスター・クライトン博士!」

「じゃあやっぱりお前、そこの墓に入ってるサウザンドワード博士のことを知らないのは片手落ちってもんだ」

「え……」

「SiNEプロトコルの生みの親だぜ?」

この嫌味な男は一体、何者なんだろう。

粗野でがらの悪い話し方、狡猾な嘘をつくろくでなしで、どこからどう見てもまともな人物には見えないけれど……

「しっかし、お前、マメに通って遊んでくれていたみたいだな。お陰で俺のサーチライトが随分乳臭い女になっちまった」

「な……」

「何だぁ、怒んなよ。ああいう女が好みなのか? 馬鹿だなぁ、これだからガキは」

アハハと笑われて、怒りに目の前が暗くなる。

「……これ以上、下らない話に付き合う気はありませんっ!!」

反射的に、踵を返して走り出す。

「あ! おい、ちょっと待て! まだ話が……うわ、おい! 待てって!」

呼び止めようとする男の言葉など、聞き入れるつもりは毛頭なかった。

「お前、そのゴーグル使うなよ! それは────」

慌てる男を無視して、振り返りもせず走り去る。

「おい……」

あっという間に闇に溶けていく少年の後ろ姿を、男はしまったという顔で見送る。

「あー……ちょっとつつき過ぎたかな」

少年の居なくなった墓地に、男の声が空しく響いた。


あんな男の言うことを、聞くことはない。

全く、サーチはあんなに可愛くて素直なのに、設計者がああいう人間だったなんて。凄い技術を持っていても、ああいうのは認められない。

ウィリアムは心の中で繰り返した。

全く全く全く、腹が立つ!

人のことを子供扱いするだけでなく、馬鹿にして!

霊園を出て、公園を一気に走り抜け、住宅街の街灯の下まで戻った所で立ち止まり、乱れた息を整えながら後ろを振り返る。

男が追いかけてくるような様子は無かった。少年は収まらないながらもホッと息をつき、それから家に連絡をした。


「あっれ、ハロルドじゃねぇか」

豪邸が立ち並ぶオークフィールズをだらだら歩いていたハロルドに、通りかかった車から声がかかった。

エルズ雑貨店のロゴマークがペイントされた深緑のワゴン車。運転席からヒョイと顔を出したのは、リオだった。

「リオ、仕事帰りか?」

「おうよ。配達帰りだよ」

「ちょうど良かった、乗せてけ」

ハロルドはニッと笑うと、返事は聞かず助手席に乗り込む。

リオはやれやれとため息をついたが、文句は言わずに車を出した。

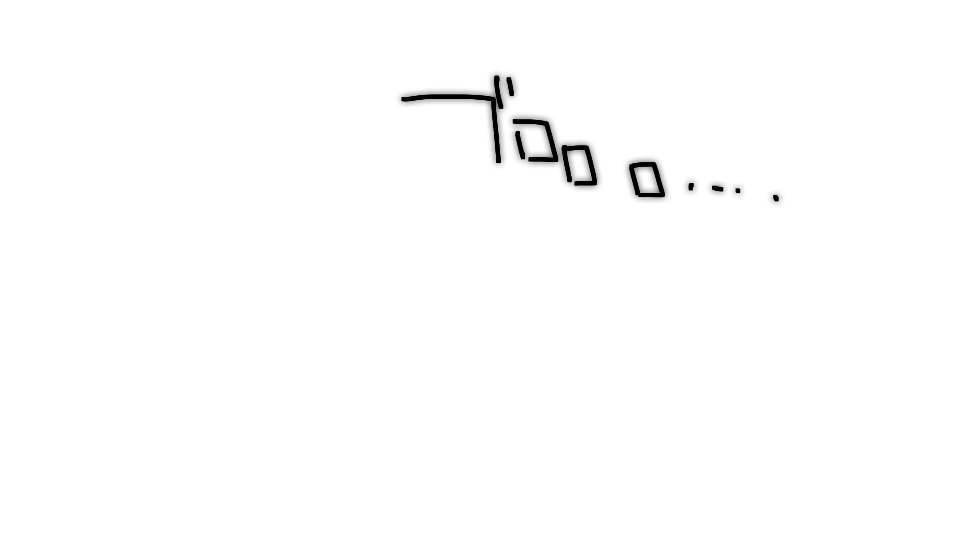

「お前、もしかして歩いて来たわけ?」

「んなわけあるか。バスだバス」

「……相変わらず車乗らねーんだな」

「いいだろ別に、めんどくせえ」

「ははぁ、良いご身分だ。相変わらず」

二人は学生時代からの友人だ。

いつまでも職に就こうとしないくせに、飄々と苦労知らずのような顔をしているハロルドと、日々、自分好みの商品を物色しては仕入れ、売れたの売れないのと大騒ぎしているリオは、根本的には似たもの同士であり、何だかんだいって昔からうまが合う。

「しかし、珍しいなこんなところ、墓参りか?」

「ま、そのようなもんだ」

「……ホントに珍しいなぁ」

分かったような分からないような顔で頷くリオの隣で、ハロルドはゴソゴソと首から下げていた愛用のゴーグルを立ち上げる。

彼がいつもこの小型コンピュータとマネーカードしか持ち歩かないことを、リオはよく知っていた。

「そういやさ、ゴーグルって最近子供に人気あんの?」

「はぁ?」

「いや、そういう機械って、買いに来るのは基本、昔を懐かしむ系のオヤジばっかじゃん?」

「それがさあ、こないだ子供に売ったんだよ。しかも、前にお前に頼まれて仕入れてたSiNEサーバのデータ処理チップも一緒に買ってってさ……」

「……もしかして、眼鏡で黒髪の生意気っぽいガキか?」

「ん? あー……まぁ、確かに、眼鏡で黒髪だったよ。生意気じゃなくて、普通に礼儀正しい子だったけど」

「うっわぁ……それだ。リオ、売るなよ馬鹿」

突然の意味不明な非難に、リオは顔をしかめる。

「なんでハロルドにそんなことを言われないといけないんだよ」

「リオ、お前は知ってるだろう。コレの使い道」

「そりゃ……や、だからさあ、珍しいなぁって思ったんだよ。1ビット・ダイビングってもう流行りだしたのかってさ」

「流行ってるわけあるかよ」

「だよなー」

「おい!」

リオの運転する車は、すべるように大通りを抜け、ヴィーナスブリッジをガイアポリスの方へと走っていく。

ハロルドは八つ当たりをやめて大人しくメールチェックか何かをしていたようだったが、やがてそれを終え、疲れた様子でシートにもたれかかる。

「しっかし、偶然っつう奴はアレだな。案外、油断ならねぇ」

「あの坊やのこと?」

友人の言葉に、周辺の事情を何となく察したらしいリオが、苦笑して尋ねる。

「まぁな。ほら、前に見せたことあんだろ、俺のSiNEクローラー」

「ああ、あのかわいこちゃんか」

「あいつがこないだ巡回先で、偶然そいつに見つかってな。んで、AIが妙に気に入ってるみたいだからさ、ちょっと好きにさせてたんだ。ガキってのは自動学習の相手にはちょうど良いし」

「ははぁ……」

「したら、あいつ、妙にマニアックな奴で、自力でサーチライトを使って1ビット・ダイビングについての俺のデータを盗みやがった」

「……あの坊や、そんな子だったのか」

リオはさすがに驚いた様子で呟いた。

「で、AIと遊ぶくらいならともかく、まさか一人で潜ったりしたらヤバイからな、教えておいてやろうと思って呼び出したんだが……」

「何が気に食わねぇのかやたらと噛み付きやがって、こっちの話を全く聞きやしない」

「もしかしてお前、その帰り?」

「ああ。まぁ、こっちには別の用事で来てたんだけどさ」

「どーせ偽名で呼び出したんだろ。しかも夜の墓に」

「いいだろ別に。感の良いガキで、しかも中途半端に技術もあるみたいだし、俺個人を特定されたりしても面倒なんだ」

「あと、あの墓はハイスクールから近いし、静かだからちょうどいいと思っただけだ。むしろ親切心だ」

「それにしてもさ、ティーンの心ってのは純粋で繊細なんだぞ?」

「お前みたいな嫌味で偉そうな奴に懐くわけねーよ。イイコイイコしてやらねーと話なんか聞かねーって。お前だって覚えくらいあるだろ」

「ねぇよ、馬鹿」

ハロルドはムッとして顔をそむけたが、それ以上反論しようとはしなかった。

「しっかし、それはさあ、偶然とはいえないんじゃねえ?」

「なんでだよ」

「今時、閉鎖後世代でSiNEに興味を持つなんてさ、もともとそういう素質があるんだよ」

「それは……」

「だから、ま、それはさ、いわば、神様のおぼしめしってやつだ」

呑気な調子でそう言って笑いながら、リオはハンドルを切って細い通りへ入っていった。

To be continued.